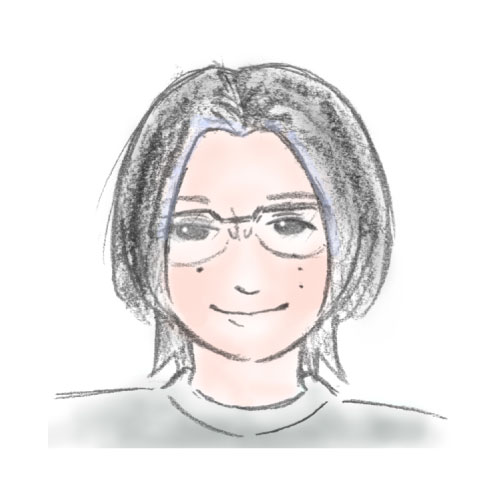心意気インタビューとは、地域の「ヒト・モノ・コト」の心意気を発見していくコンテンツ。
今回の取材先は、山里Magari(やまざとマガーリ)の シェフ高須孝博(たかすたかひろ)さんと、ワインソムリエの綿谷真由美(わたやまゆみ)さん。
山里Magariさんは、2025年5月に米沢市関根の山間にオープンした、古民家をリノベーションしたイタリアンレストランです。イタリア料理と、米沢に根付く「かてもの」を掛け合わせることで生まれる新たな魅力や、今後の可能性についてお話を伺いました。
この記事で読めること
山里Magari 高須孝博さん、綿谷真由美さんへインタビュー
お店の歴史や経緯について教えてください。
創業は2006年1月、東京都内にオープンしました。私は当時、OLとして働きながらワイン学校に通っていて、ソムリエの資格も取得しました。「せっかく学んだ知識を何かに活かせないか」と考えていた時期に、イタリアで高須君と出会ったんです。当時、私はフィレンツェでワイン造りを学んでおり、高須君は現地のレストランで働いていました。とはいえ、その頃は「日本人会」という集まりで、3回くらい顔を合わせただけだったんです。
それから5年ほど経って、私は日本に帰国し、お店を開く準備を始めていました。場所やシェフを探していた時期に、友人から「高須が日本に帰ってきたよ」と聞いて、思い切って連絡を取ってみたんです。そして、再会して近況を話すうちに、自然と「一緒にやろう」という流れになり、そこから約20年、一緒にお店を続けています。

日本人会とはどのような集まりだったのですか?
綿谷さん
フィレンツェは芸術とアートの街で、日本人会に参加していた方々も、さまざまな分野の勉強をしていました。イタリア語をはじめ、革細工やジュエリー、大理石のモザイク加工などが多かったですね。当時は日本人の滞在者も多く、2~3か月に一度のペースで集まって、交流したり情報交換したりしていました。参加者の学んでいる分野が違うので、集まると本当にさまざまな話題が飛び交って、面白かったです。
その中で、料理ができるのは高須君だけだったんです。寿司や唐揚げを作ってくれて、その塩加減がとても良くて印象に残っていました。
それがきっかけで、「お店を一緒にやらないか」と声をかけたんです。
料理の道に進まれたきっかけを教えてください。
高須さん
小さい頃から職人に憧れていて、中学生のとき、調理師の実習に興味本位で参加したのがきっかけです。そのときにとても刺激を受け、「料理の道に進みたい」と思うようになりました。高校卒業後は、大阪の辻調理師専門学校に進学しました。
日本料理やフランス料理は、ちょっと厳しそうなイメージがあって、自分には合わないかなと思ったんです。そこで、中華料理かイタリア料理のどちらかで悩んだのですが、中華包丁は大きくてちょっと苦手で…。結果的にイタリア料理を選びました。
綿谷さん
消去法かい!(笑)
とは言うものの、実は彼が海外で働いた2店舗目に「イル・ブッテロ」というお店があって、そこの料理長・ジョバンニさんにすごく影響を受けたそうなんです。その出会いがあったからこそ、彼は本格的にイタリア料理の道に進んだんですよ。
そういう話を伝えてほしいんですよね。中華包丁が怖いという理由じゃなくて(笑)。
高須さんは、一緒にお店をしようと言われたときは驚きましたか?
高須さん
それほど驚きませんでしたね。「一緒にやってみたい」という軽い気持ちで始めました。
綿谷さん
むしろ、あまりに気軽にOKしてくれたので、私の方がびっくりしちゃいました(笑)。当時の私はOLで、飲食店の経営は初めてだったんです。そのため、プロの料理人が一緒にやってくれるとは思ってもいませんでした。 「イタリアの家庭料理を出すお店をやりたいんですけど、一緒にやりませんか?」と声をかけたら、高須君が「あ、いいですよ」と、あっさり引き受けてくれて。私は、「もしダメだったらまたOLに戻ればいいや」くらいの気持ちでいたので、本当にありがたかったですね。
その時、「ああ、職人さんってこういう強さがあるんだな」と実感しました。

何か新しいことを始めるとき、最初から力が入ってしまう方も多いですが、私はこの20年間やってきて、「今日より明日が少しでも良くなればそれでいい」と思うようになりました。最初は肩の力を抜いて始めて、続けていく中でだんだんとプロになっていく。そんな道のりがあってもいいと思うんです。
お料理を提供してきて、一番嬉しかったエピソードはありますか?
綿谷さん
もちろん、どんな場面でもお客様に喜んでいただけるのが一番うれしいのですが、最近では、南原で「里山ソムリエ」として活動されている黒田三佳さんのお嬢様の結婚式が、とても印象に残っています。 実は彼女は高校の同級生で、私を米沢に引き寄せてくれたようなものなんです。
そして、米沢に来て最初の仕事が、黒田さんのお嬢様の結婚式だったんです。本当に光栄でした。人生で最も華やかな時間にご一緒できて、さらにそのお役に立てたというのは、まさに仕事冥利に尽きるなと感じました。
また、普段はワインソムリエとしてお客様と接していますが、料理を召し上がった方が「高須の料理が一番」と言ってくださると、やっぱり嬉しくなりますよね。
米沢に移住する決断に至ったきっかけを教えていただきたいです。
綿谷さん
米沢を初めて訪れたのは2022年、黒田三佳さんのお誘いがきっかけでした。彼女はとても行動力のある方で、米沢に到着したことを連絡したら、「今日はブドウの収穫をするから手伝って」と突然言われまして(笑)。その日のうちに、南陽市にある「グレープリパブリック」さんというワイナリーで、デラウェアの収穫を手伝うことになったんです。まさか初めて来た日にそんな体験をするとは思いませんでした。
その後も米沢を訪れるたびに、自然の豊かさや美しい景色、城下町としての歴史や文化の深さにどんどん惹かれていきました。なにより、ここで暮らしている人たちが生き生きと生活している様子を見て、「こんな場所で暮らせたら素敵だな」と感じるようになったんです。
そして、移住の最終的な決め手となったのが、2023年の5月ごろ。東京から仲間を20人ほど米沢に招いて、米沢でやりたいことと私の想いを伝えたところ、みんなが「すごくいい!」「面白い!」と背中を押してくれたんです。それから黒田さんに「畑付きの家を探してください」とお願いして、今に至ります。

米沢市の好きなところや、魅力はどんなところですか?
綿谷さん
やはり、城下町ならではの文化と歴史があるところが魅力ですね。そして、文化や歴史が根付いている場所にはおいしい食もある、そんな印象を受けました。米沢は、何を食べても本当にハズレがなくて、美や食に対する意識がとても高いと感じます。だからこそ、お店としてもとてもやりがいがあります。ただ大量に料理を出せばいいのではなく、普段から良いものを食べ慣れている方々にお出しするという、ある意味での“緊張感”もありますね。
それに加えて、人が優しく、そしてとても“しっかりしている”という印象があります。仕事に対しても、暮らしに対しても真面目で丁寧なんです。そうした性格だけでなく、暮らし方そのものがすごく好きですね。たとえば雪おろし。1軒の家だけがやるのではなく、地域のみんなで協力してやるんですよね。「同じ大変さを一緒に乗り越えよう」という気持ちが自然と根付いていて、そういうところがとても素敵だと思います。
もちろん、食材が素晴らしいというのも、米沢の大きな魅力のひとつです。
米沢市に移住して何か変化などはありますか?
綿谷さん
すごく変わったなと思うのは、高須君の表情ですね。
東京にいた頃は、どこか疲れたようなしんどそうな顔をしていたのですが、米沢に来てからはまったく違います。今では朝5時台に起きて、畑仕事や小屋の整理など、いろいろなことを始めていて。「本当に自分の好きなことで、ワクワクしながら朝を迎えているんだろうな」と感じます。毎日、自分のやるべきことが“好きなこと”になっている。東京にいた頃は、私が「これやって」と言えば“仕事だからやる”という感じだったのですが、今では自ら動いてくれるようになって、主体性が出てきたように思います。これが一番大きな変化かもしれません。

それから、米沢には本当にゆったりとした空気が流れていて、急かされることも、無理に早歩きするようなこともありません。そういう意味でも、ここは彼にとってとても合っている環境なんだと思います。彼は以前、イタリアのフィレンツェに長く滞在していたのですが、時間の流れ方や使い方など、米沢の空気感がフィレンツェと少し似ているようです。
畑ではイタリアの食材も育てる予定ですか?
綿谷さん
イタリア野菜については、生産者の方がいらっしゃるので、畑では基本的に自分たちが日常的に食べるものを育てる予定です。お料理で使う食材は、敷地内にある山菜や、「かてもの※」を中心に取り入れていくつもりです。畑の野菜も、出来が良ければメニューに取り入れることがあるかもしれません。関根や南原にも、素晴らしい食材を育ててくださる方が大勢いらっしゃるので、食材については地域の方々にお任せしている部分が大きいですね。
※かてもの… 上杉鷹山が飢饉に備えて記した食の手引書。そこで紹介される野草や山菜を指すこともある。

米沢の暮らしで大変なところはありますか?
綿谷さん
カメムシですね。それ以外は特にないです。雪が積もるのはあまり気にならないんですけど、カメムシだけはどうしても気になってしまって…。一匹でも見つけると、「絶対に見逃したくない!」という気持ちになります。暖かくなってくる3月や、稲刈りが終わる10月ごろになると、大群で飛び始めて押し寄せて来ました。初めてのときは本当にびっくりしましたね。最初はガムテープで地道に捕っていましたが、最終的には部屋の中や天井まで徹底的に掃除機で吸ったり、高須君が外回りを掃除したりして、ふたりで頑張って対処していました。
米沢らしさとイタリアンの組み合わせにはどんな魅力があると思いますか?
綿谷さん
やはり「地産地消」が一番の魅力ですね。イタリア料理はフランス料理のような“ソース文化”とは違って、地元で育った素材をそのまま調理する、素朴で自然な料理が中心です。いわゆる“家庭料理”が一番おいしい、という世界観なんです。そこが米沢ともすごく似ているなと感じています。
米沢には良い素材が本当に身近にあります。みずみずしくてフレッシュなものを、シンプルな調理法で活かす。これはまさにイタリア料理にぴったりなんです。唯一、身近にないものといえばオリーブオイルと柑橘類くらい。そこは少し我慢が必要ですが、それ以外の素材は、世界中を見渡しても上位5%に入るような素晴らしいものが揃っていると思います。
中でも「米沢牛」は、まさに世界レベルの食材ですね。実は、米沢牛の多くは地元にとどまっていて、その多くを県外から訪れた方々が召し上がっているんです。それほど価値のあるブランドだということ。飼育期間が長いため、脂の質が良く、溶けやすくて軽やか。海外の人にもきっと喜ばれる味わいです。
また、米沢の寒暖差がもたらす野菜や果物の味の濃さ、そして山菜やキノコといった山の恵みも、世界に誇れるレベルだと思います。海がない地域ではありますが、庄内や宮城県など東北沿岸部から新鮮な魚介類が届く市場があるので、困ることもありません。さらに、関根の山では鉄砲水が湧き出したことをきっかけに、引かずに湧き続ける水を利用して、ため池でニジマスやヤマメを養殖している方がそばにいます。旬となる夏には、川魚もメニューとして提供できそうです。
今後かてものを使用して挑戦したいことはありますか?
綿谷さん
「かてもの」には、少し独特な香りを持つ野草もあるので、そういった“香りもの”は、モクテルやソースに活用できると思っています。前菜からメインディッシュまで、ソースとして使ったり、生地に練り込んだり、素材そのものの形を活かしたりと、いろいろな使い方ができるはずです。モクテルのようなドリンクにも応用できますし、可能性を感じています。

「かてもの」を使用したモクテルについて教えてください。
綿谷さん
「モクテル」は、ノンアルコールのカクテルのことで、特にコロナ以降、アルコールではなくノンアルコールを選ぶ方が増えていて、東京ではモクテルを楽しむ方も多くなってきました。米沢のような車社会では、お酒を飲めない・飲まないという方も多いので、そういった方にも楽しんでいただけるように、季節ごとに「かてもの」を使ったモクテルを作っていきたいと考えています。甘いジュースのようなものではなく、甘さを控えめにして、「かてもの」ならではの香りや味わいを感じられるような、ちょっと複雑さのある味に仕上げたいですね。季節ごとに2〜3種類ほど、提案していけたらと思っています。
マガーリさんのお料理とワインの魅力を教えてください。
綿谷さん
高須君の料理の魅力は、やさしさにあると思います。素材の味を決して殺さず、丁寧に、やさしく引き出してくれるところですね。「出ず入らず」という表現がぴったり。主張しすぎず、かといって引っ込みすぎない絶妙なバランスや“緩急”が彼の料理にはあるんです。これまで様々なシェフの料理を食べてきましたが、強い味の人は最後まで強すぎたり、逆に弱すぎると物足りなさが残ったりと、なかなかバランスが難しい。でも高須君の料理は、その点でとても完成度が高いと感じています。
料理とあわせるワインにも、これまではイタリアワインを合わせてきました。イタリアは“テロワール”と呼ばれる自然環境にとても恵まれた土地で、太陽をたっぷり浴びたブドウは糖度が高く、結果としてアルコール度数も高くなりがちなんです。東京でお店をやっていた頃は、その中でも比較的やわらかい風味で、アルコール度数の低めなワインを選び、高須君のやさしい料理に合わせていました。そして今、山形に来て地元のワインが使えるようになったことも、大きな魅力の一つです。やはり、日本人が作るワインって繊細でやさしいんですよね。使用されるブドウの品種も、タンニンが強く出すぎるようなものではなく、やわらかく穏やかな味わいのものが多いんです。そういった繊細な山形のワインと、高須君のやさしい料理は、本当に素晴らしいマリアージュを生み出してくれると思っています。

ブドウの品種や育てる土地によって味や風味も変わってきますか?
綿谷さん
もちろん変わります。たとえば南陽ではデラウェアなどを栽培していますが、山の東斜面に太陽がしっかり当たる地形になっていて、日照条件が良いんです。ただ、日本は雨が多いため、ブドウは棚上げして雨がかからないように工夫されています。一方イタリアは、天候や降水量など、あらゆる面でワイン造りに適した環境が整っていて、土壌にも恵まれています。そうした条件の中で育つブドウは糖度が高くなるため、結果としてアルコール度数の高いワインが多くなるんですね。
アルコール度数が高く、タンニンもしっかり感じられる力強い「バランスの良い重厚な赤ワイン」は、1990年頃のバブル期に大流行しました。ボルドーやイタリアの赤ワインがまさにその代表格でした。しかし今は、時代の感覚が大きく変わってきています。
たとえばファッションで言えば、かつての肩パットのような派手さよりも、スレンダーでミニマルなバランスが好まれるように。料理で言えば、バターをたっぷり使うよりも、オリーブオイルで軽やかに仕上げるようなスタイルへ。
消費文化も大量消費から、リサイクルやサステナブルな方向へとシフトしています。食の世界でも同じで、健康や環境に配慮した「持続可能な食」のニーズが高まっていて、いわゆるSDGs的な視点が重視されています。

そういった今の時代に、日本のワインはとても理にかなっていると思うんです。輸送のマイレージもかからず、すぐ近くで丁寧に造られたワイン。そして、オリーブオイルを使ったヘルシーでやさしい料理にもよく寄り添ってくれる。そう考えると、日本のワインは“1周回って”今、世界レベルに来ていると思います。
地産地消のワインを提供し続けるとどのような可能性が生まれると思いますか?
綿谷さん
米沢は、これから「いちばん新しい町」になっていくんじゃないかと思っています。
バブル期には、パリを目指してエルメスを買い、ローマを目指してプラダを買うような時代がありました。でも今は、そうした“消費の象徴”のような時代から、「脱・消費社会」へと変わりつつあります。
そんな中で、地元で採れた食材を使った料理と地元で造られたワインを、ゆったりと楽しむ。そういう丁寧で持続可能な暮らし方こそが、今、世界的な価値として再評価されていると思うんです。特に「かてもの」は、どこにでもあるものではありません。米沢という土地に根付いた独自の食文化です。その「かてもの」にフォーカスし、深く突き詰めていくことで、他にはない“唯一無二の価値”が生まれる。これは誰にでもできることではないし、本当にありがたいチャンスだと思っています。そうした取り組みが、結果的に「世界レベル」へとつながっていく可能性は十分にあると感じています。

今後もイタリア産のワインを提供されますか?
綿谷さん
もちろん、イタリア産のワインを今後もご提供していきます。東京や他の地域・国から来られたお客様には、ぜひ山形産のワインを味わっていただきたいと思っていますし、逆に地元・米沢の方にはイタリアなど海外のワインを楽しんでいただくのもいいなと考えています。
基本はあくまでも料理との相性が一番大切です。たとえば、山形・高畠の「バリック」は、国際品種であるシャルドネを樽熟成したものです。樽の内側を焼いて香りを移すことで、ウイスキーのように「バニリン」と呼ばれる、バニラや焼き菓子のような香りがつくのが特徴です。同じくシャルドネを樽熟成したイタリア・シチリア産のバリックもあります。南イタリアの陽光をたっぷり浴びたシチリアでは、糖度と酸のバランスがよく、ボリューム感のある味わいに仕上がります。比較すると、高畠のバリックの方がより繊細でやさしい印象です。お好みによって、しっかりとした樽香のワインが飲みたい方にはシチリアのバリック、繊細なペアリングを楽しみたい方には高畠産のバリックをご案内しています。たとえば、白身魚のサクラダイのカルパッチョには、高畠のバリックを合わせるのが相性抜群ですね。とはいえ、基本的には「お客様の好みに合わせてご提案する」という姿勢です。

ワインと料理の“意外な組み合わせ”も魅力のひとつです。たとえば、塩気のあるゴルゴンゾーラチーズに甘いハチミツをかけるように、ワインの世界でも「甘い × しょっぱい」の相乗効果があります。濃厚なチーズに極甘のデザートワインを合わせると、意外な美味しさが生まれるんです。
また、ノスタルジーを大切にしたペアリングもあります。たとえば「山形のご飯と、お母さんの味噌汁や漬物が大好き」という方には、地元・高畠のワインを。「昔イタリア旅行でシチリアでタコを食べた思い出がある」という方には、シチリアのワインをご紹介します。味だけでなく、記憶や想い出に寄り添うワインの出し方も大切にしています。
春にはロゼワインもおすすめです。イタリア南部・カラブリア州の「ガリオッポ」という品種を使ったロゼがあり、この地域はブーツ型のつま先にあたり、海と山が近く、ワイン造りに難しい地形です。それでも、土地に根ざしたワインと食文化が残っていて、たとえばカラブリア産のワインは、名産である唐辛子料理に合うように造られています。これは日本にも似ているところがありますね。たとえば四国・四万十川の地域では、地元の天ぷらに栗焼酎を合わせる文化があるように、その土地の食と酒が自然に寄り添っているんです。イタリアも日本も、地元の食には地元のお酒という精神がとてもよく似ています。

山形・朝日町の「マスカット・ベーリーA」もご紹介したいワインのひとつです。少し他品種とのアッサンブラージュ(ブレンド)になっていますが、日本を代表する赤ワイン品種で、ほどよいタンニンと華やかな果実味があり、前菜からメインまで幅広く合わせられます。たとえば、前菜から1本のワインで楽しみたいという場合にも最適です。特に野菜料理やカルパッチョなど、ワインのペアリングが難しい前菜には、最初は冷やしてタンニンを感じさせずに提供し、徐々に温度を上げて後半に米沢牛と合わせることで、ワインの表情が変化していく楽しみ方もご提案しています。
イタリアワインも山形のワインも、その土地の風土と文化を映し出すもの。お客様一人ひとりの味の好みや思い出、季節、料理に寄り添いながら、その時にぴったりの一杯をご案内していきたいと考えています。
イタリアワインが好きな方もいれば、フランスのボルドーなどしっかりとしたタンニンのあるワインを好む方もいらっしゃいます。ただ、ボルドーのような重厚なワインが好きな方に、料理との相性を考えずにそのままお出しすると、あまりご満足いただけないこともあります。ですので、そういった方向けには、少し重めのワインもご用意しています。ソムリエというのは、お客様とお話しするほどに、その方のデータがどんどん蓄積されていくものなんです。お好みや思い出、お話の中にあるキーワードから、その方にぴったりの一本をご提案できるように心がけています。

どんなお店にしていきたいとお考えですか?
高須さん
お客様が楽しく、ゆっくりと過ごせる空間をつくっていきたいですね。
綿谷さん
私も基本的には同じ気持ちですが、少し“野心”というか“野望”があるんです。米沢には、米沢牛やラーメン、お蕎麦など、すでにたくさんの名物がありますよね。その中に、「第4、第5の選択肢」として、“米沢イタリアン”というジャンルを根づかせたいと思っています。まずは2人でスタートしますが、1年後くらいには仲間を増やして、米沢イタリアンを他の地域にもどんどん広めていきたい。そして、いずれは「米沢といえばイタリアンだよね」と言われるようになりたいんです。

また、「かてもの」を中心に、米沢でしか味わえない食材を使った料理で、世界中の人に来ていただけるようなお店にしたいという夢もあります。
米沢藩・第九代藩主、上杉鷹山公が刊行した「かてもの」。これは、江戸時代に飢饉に備えて食べられる野草をまとめた手引書として知られています。その「かてもの」の令和版として、黒田三佳さんが今年の春に「森とかてもの」という本を出版しました。植物学者ではない彼女だからこその視点で、「かてもの」への新しいアプローチを提案していて、まさに「今」だからこそのタイミングだったと思っています。

もともと私も「かてもの」を使った料理をやりたいと考えていましたし、東京から遊びに来てくれる友人とも「こういう食材で料理を出せたら面白いよね」と話していました。運良く、近くには「かてもの」に詳しい信頼できる友人もいて、「これは食べられる」「これは避けたほうがいい」といった知識も分けてもらえます。
そういった繋がりや想いをもとに、米沢でしか生まれない、唯一無二の“米沢イタリアン”を育て、広めていくことが私の野望です。
“米沢イタリアン”として、米沢市の魅力を世界へお届けするようなイメージでしょうか?
綿谷さん
そうなっていくと嬉しいですね。ただ、実際に米沢にいると、なかなか自分たちの魅力を客観視できないことがあるんです。米沢に移住したばかりの頃、「なぜ米沢なんですか?」とよく聞かれましたが、米沢は本当に素敵な場所。けれど、その良さは外から来ないと気づけないことが多いんですよね。
イタリアでも同じようなことがありました。高須君がいたトスカーナ地方は、今でこそ“ワインの丘”として世界遺産に登録され、世界中に知られるようになっていますが、そうなったのは1980年代の終わり頃からです。当時、何とか地域を活性化しようとイタリア政府が助成金を出し、地元の農家の方々が「アグリツーリズモ(アグリカルチャー × ツーリズモ)」、つまり“農業と観光を掛け合わせた農家民泊”を始めました。現在でも「農業の収入を観光が超えてはならない」といった細かなルールはありますが、その取り組みが地域を変えるきっかけになったんです。
私がイタリアを好きになったのも、その体験がきっかけでした。職業柄、年に一度2週間の休みを取るルールがあり、その時間を使って語学学校に通いながら、一人でイタリアの農家民泊に泊まってみようと思ったんです。一人旅でしたが、毎日収穫したての野菜で作られる料理や、有名なキャンティワイン、ブドウ畑が広がる美しい景色、そしてフィレンツェやシエナといった歴史と文化のある街が車で1時間以内にある環境——すべてが本当に魅力的でした。
トスカーナ地方のように、米沢のことを好きになってくれる人が、きっと世界中にいると信じています。だからこそ、米沢の魅力をより多くの方に届けられるよう、“米沢イタリアン”や、鷹山公の教えを活かした取り組みを、これからも続けていきたいと思います。
取材を終えて 山里Magari様の心意気とは
米沢の食を世界へ
現代にまで受け継がれる上杉鷹山公の教えを、ただ見つめるだけでなく、これからも失うことなく未来へとつなげていく。米沢で暮らす人々にとって、あまりにも身近で気づかれにくい「かてもの」を、新たな食文化の選択肢として再発見し、米沢の皆さんに、そして世界へと伝えていく。
米沢に惚れ込み、移住という決断を経て、古民家でイタリアンレストランを営むお二人の挑戦と覚悟。その姿に、米沢の食の未来が重なって見えました。