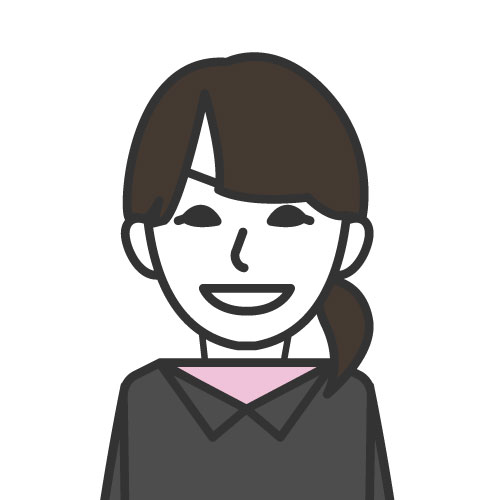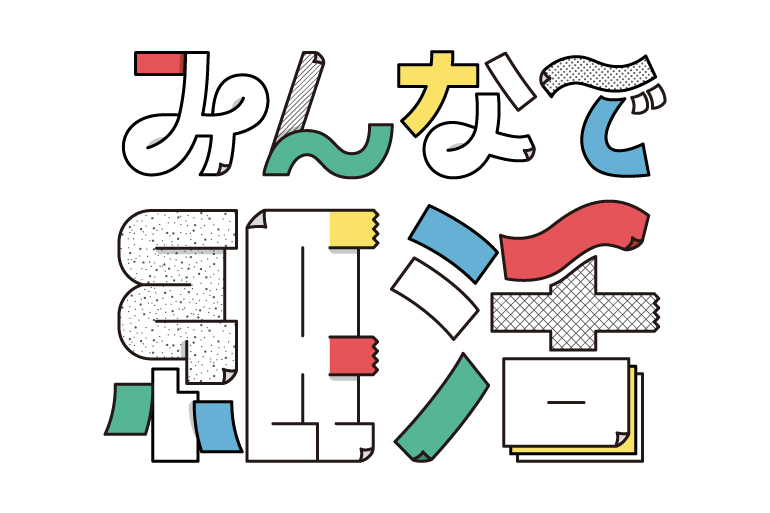心意気インタビューとは、地域の「ヒト・モノ・コト」の心意気を発見していくコンテンツ。
今回の取材先は株式会社新田 5代目新田源太郎さん。
株式会社新田様は、長年織物業を営んできた老舗の企業です。
地元の伝統工芸である「米沢織」に携わりながら、紅花染めをはじめとする伝統的な技術を受け継ぎ、現代に活かしたものづくりを行っていることで知られています。
この記事で読めること
株式会社新田 5代目新田源太郎さんへのインタビュー
紅花と関わるようになったきっかけを教えてください
昭和38年頃、新田の3代目・新田秀次(しゅうじ)が、紅花染めを研究していた鈴木孝男先生と出会って、そのご縁から紅花染めを始めることになりました。
創業は明治17年で、機屋(はたや)として織物業を始めたのもこの年です。もともと、上杉鷹山公が250年前に殖産振興としてスタートしたのが米沢織です。その米沢織を武士の婦女子が従事しました。婦女子も含めて代を重ねることによって、米沢藩というものが財政を健全化していくという流れになるわけです。その時には家計も織物に従事していました。
武士の家柄だったため、何代目から織物に関わり始めたのか、正確な時期は記録がなく定かではありませんが、明治になり武士制度もなくなったことによって、手に職となる織物業を始めたということになります。

武士から織物屋として始めた頃には、すでに袴を作っていました。昔の米沢は男物の産地で、上杉藩の鷹山公が始めた殖産振興のもと、米沢織は武士向けの織物として広く用いられるようになりました。
裃(かみしも)の生地であったり、中に着る着物だったり、その延長で明治に入ると袴を本格的に作っていくようになります。このように織物業を営む中で、3代目・新田秀次が紅花と出会うことになる訳です。
その当時は紅花も含め、染色を行うところがなかったので、自分達で研究を重ねるしかなかったと聞きます。そうした中で「紅花つむぎ」を発表するに至った、というのが大まかな経緯です。
ちなみにこの建物が建てられたのが、昭和の始まり、つまり今年でちょうど100年になるんです。実は私が着ている法被は、ここの建物の棟上げのときに使われたものなんです。だから100年以上前の「法被」ということになります。

昭和元年にはもうこの建物が完成していたはずなので、今年がちょうどその節目の年なんですね。そういう意味も込めて、せっかくだからこの100年という歴史と建物をうまくアピールできたら楽しいかな、と思って今回着てみました。ちなみに、この法被は大事に保管されていたようで、まだ結構な枚数がちゃんと残っているんです。
紅花への想いと、伝統を守るうえで大切にしていることを教えてください
新田が織物業を始めて私で5代目になります。
大切にしていることは、「不易流行」という言葉にも通じますが、変えてはならない部分と、変えていかなければならない部分の両方を意識することです。
ターニングポイントとしては、祖父が「紅花染め」と出会ったことが挙げられます。もともと男物の産地であり、弊社でも袴などさまざまな男物を織っていましたが、それがきっかけで女性物の着物をメインに作るようになりました。これは非常に大きな転機だったと思います。
一方で常に変化を意識しながら、ものづくりに励む姿勢も大切です。その時代の空気を感じ取りながら、もの作りをしていかなければならないと考えています。
紅花のどんなところに魅力を感じていますか?
紅花の魅力は、何千年もの長い歴史を持つ染料として、今もなお使われ続けている点だと思います。一時は生産が途絶えたとも言われていますが、さまざまな時代の変化を経ても、こうして染色の文化が受け継がれているというのは、とても貴重なことです。
中でも最大の魅力は、その「色」ですね。本当に美しく染まり、その色合いそのものが魅力的で、そうした美しさには、歴史の重みとともにロマンも感じられます。

紅花は昔から非常に高価で、「金と同じ価値があった」「金の10倍に相当した」とまで言われるほどでした。それほどまでに、紅花は貴重な染料で、一般庶民の手に届くようなものではなかったのです。そんな紅花が、今こうして再び花を咲かせるように染色に使われ、多くの人の目に触れるようになっていることが、まさに私が感じている“ロマン”です。
江戸時代やそれ以前の室町時代などでは、紅花で染められたものは、一部の特権階級しか目にすることができなかったとされています。そう考えると、今の時代に誰もがその美しさを実際に見られるというのは、とても貴重なことだと思います。
「紅花染め」の魅力や特徴について教えてください

「紅花染め」とは、紅花そのものが非常に歴史のあるもので、起源は4000年以上前にさかのぼるとされています。シルクロードを経て日本に伝わり、魏志倭人伝の時代にはすでに存在していたとも考えられています。そんな長い歴史を持つ一方で、明治以降には衰退してしまったのです。
紅花が化学染料に押されてしまったという背景もありますし、その後、戦争が始まり、農業政策の影響で紅花自体を育てなくなってしまいました。そうなると、当然ながら染織もできないという状況になったのですが、そのような中で祖父が紅花染めと出会い、染色を始めることになりました。
祖父が最初に取り組んだ「紅花染め」というのは、紅花だけで染めるのではなく、「重ね染め」といって、さまざまな色を重ねることで色のバリエーションを出すというものでした。また、どういった作品として世に生み出すのかという点も非常に大切にしていました。
ですから、ただ「紅花染めをした」というだけではなく、どのようなものをイメージしてもの作りを行ったのか、その背景を大事にしていました。なぜその色を選ぶのかといった点を含めて、「作ればいい」ということではなく、背景を意識したもの作りをしていたのだと思います。
紅花染めを続ける上で、大切にしている譲れないこととはなんですか?
やっぱり、米沢織も紅花染めもそうですが、何よりも「続けていくこと」が大切だと思っています。それをどういう形で続けていくか、時代に合わせながら考えることも必要ですし、あまり堅苦しく考えすぎず、時代とともに自然に歩んでいくことが大事なんじゃないかなと感じています。「これが絶対だ」とか「こうあるべきだ」と決めつけるよりも、続ける中でその時代に寄り添って変化していく。その柔軟さも含めて、継続することに意味があるのかなと思っています。

一貫生産化しているとお聞きしましたが、全て作られているのですか?
すべてを自社で生産しているわけではありません。山形県の生産組合というところに依頼をして紅花を作っていただき、購入もさせていただいています。それは非常に重要なことで、自社だけでなく、他の生産者の作り方にも統制が取れていないと、生産が結局安定しません。そういった意味でも、生産組合から購入するということは大切で、それは長年続けている取り組みです。
生産組合とは、祖父の代からずっとお付き合いがあり、組合ができて以来、長年にわたって紅花を購入させていただいています。ただ「購入しているからそれでいい」という話ではなく、今では、会社の行事のようなかたちで、みんなで種まきから花摘みまでを一緒に行っています。そうした関わり方も、私たちにとっては重要で大切なことだと思っています。

自分で植物を育てていると、成長の様子が分かるので自然と愛着も湧いてきます。そして最終的には、そういった経験が一貫生産につながっていくんです。つまり、花を育てるのはもちろん、染めや織りまで、すべての工程を自分たちで手がけることで、もの作りへのこだわりを持って取り組むことができるようになると信じています。
一貫生産を進める中での苦労は?
結局のところ、「苦労」と言えるほどの苦労はないというか、自分ではあまり苦労だとは感じていません。それが当たり前のことだと思っています。最終的に完成する形が見えているので、それに向かってもの作りに取り組んでいる感覚です。ですから、「ここが大変だからやめよう」というよりも、「良いものを作るためにどうするか」という視点で動いています。
大切なのは、「省く・省かない」という判断ではなく、完成までのプロセスそのものだと思っています。だからこそ、そのプロセスに丁寧に、しっかり向き合って取り組まなければならないと感じています。工房として活動している部分もあれば、会社として動いている部分もありますが、最終的には一人ひとりの力が集まって、ひとつの作品が完成します。
だからこそ、今は「ものづくりのチーム」としての意識を強く持って取り組んでいます。
地域の方々と関わりを持つ上で、意識してることはありますか?
米沢という土地で企業として成り立ち、141年続けてこられたのは、紅花だけでなく、やはり地域のおかげだと思っています。長年この地に根付いてきたからこそ、今も続けられている部分があります。
地域には何かしらの形で還元していきたいですし、私たちの仕事にも興味を持っていただけたら嬉しいと思っています。
一方で非常に残念ではありますが、米沢織については正直なところ年々事業者や従事者が減ってきているというのが現実です。4〜50年前には身近な存在だったと言われています。各通りに1軒はあるくらいたくさんあったのに、今では正直ほとんど見かけなくなってしまい、とても寂しく感じます。だからこそ、『私たちは今も変わらず続けているんだ』ということを、まずは地域の方々に知っていただきたいんです。
米沢織という存在感をアピールすると共に、もっと身近に感じていただいて、「米沢に織物や着物を作っている工房があるんだ」ということを知ってもらいたいです。そうした想いが当社主催のイベントといった形となり、現在は毎年7月の第2土曜日に継続して開催しています。その日は一般の方にも工房を開放し、社員みんなで「おもてなし」をしながら、来ていただいた方々に楽しんでもらう場として提供しています。
現在注力されているファブリックブランドについてお聞かせください

「ファブリックブランド」を作ろうと思って始めたというよりは、最初はサンプルを試しに織ってみたり、使わなくなった糸をどう活かしてモノに変えていけるか、というところからスタートしました。
つまり、「ブランドを立ち上げる」という目的よりも、「素材を無駄にせず、きちんとお客様に届けられる形にして提案していく」という考え方が強くありました。

基本的に、どんなに小さな生地や糸でも捨てることは一切なく、すべて保管しています。そして、「これをどう活かせるか」を考えるところから製品づくりが始まります。完成度を高めながら形にしていく中で、結果的に“ブランド”として見えるようになっていった、という流れです。
また、同じものを大量に作るのではなく、素材の個性を活かすことで「一点もの」を作る、むしろ一点ものしか生まれない、というのも大きな特徴です。それは、廃棄されるはずだった素材を活かすからこそ生まれる価値であり、私たちが大切にしている意識でもあります。
「一点もの」に込められた想いを感じる楽しみとはなんですか?
素材は「絹」であり、その絹は蚕が命をかけて糸をはいてくれたものです。そう考えると、その原料一つひとつを無駄にせず、大切に使い切ることが、作り手としての“使命”だと感じています。
絹を使って織物をつくるというのは、ただの作業ではなく、命や手間の重みを引き継ぐ行為でもあります。だからこそ、できる限りすべての素材を生かし、いろいろな方の手に届けることが重要だと思います。
実際、通常の製作よりもかなり手間はかかります。本来なら捨てられてしまうような残りの素材を、改めて集めて使うので、効率だけを考えれば「新しい糸でさっと織った方が早い」んです。でも、あえてそうせず、時間と手間をかけてでも素材を最大限生かす。そこに私たちのこだわりがあります。 人手の効率よりも、素材を大切にする。その価値観に重きを置き少しでも生かしていく。そんな姿勢こそが、ものづくりの根本にあります。
自分たちが作ったものが、誰かの心を少しでも豊かにしたり、手に取った方が嬉しい気持ちになったり、その場の雰囲気を華やかにしてくれるような存在になってくれたら、本当にうれしいと思います。実際に使っていただく中で、そう感じてもらえたら何よりですね。
小学生向けの活動に力を入れているのは、なぜですか?
今は学校のカリキュラムの中でも、昔より地域に関する学びや、地元の文化に触れる機会が増えてきています。そうした背景もあって、私たちもできる限り協力させていただいています。
将来的には、子どもたちが何十年後かに地元へ戻ってくるとか、あるいは外に出たとしても「自分の地元ってすごいな」と誇りに思えるようになってくれたら嬉しいです。
そういったきっかけの一つとして、私たちの活動が少しでも役に立てれば本当にありがたいですし、やりがいを感じます。 結局のところ、「続けていくこと」の中に、そうした思いも自然と込められていくんじゃないかなと思っています。
今後の展望、やってみたいことはなんですか?
今後のビジョンは、やはり大きくすることより何度も言いますが、「続けること」ですかね。その精神的なところで、例えば他の方に楽しんでもらうとか、文化とか歴史を継承したり、弊社の工房の理念というのが「物づくりを通じて歴史・文化・伝統を継承し、全ての人に喜び、やすらぎ、幸せを提供する」というのを掲げているんですけど、結局のところそこに全部行き着くというか。歴史的なところも含め伝え続け、それが最終的に製品という形で知っていただくことで、心の豊かさにも繋がってもらいたいです。
「続けること」に込める想いと、未来への願い
もちろん未来のことは誰にも分かりませんし、うちの家業も、いつまで続けられるかは正直分かりません。それに“会社”というものは、いつか必ず終わるものだとも思っています。でも、終わらないものもあると思うんです。それは“精神”であり、人から人へとつながっていく想いや姿勢です。そこにこそ、本来残っていくべき価値があるんじゃないかと。鷹山公の教えにしても、結局そうした「精神の継承」が今に伝わっているからこそ、多くの人の心に残っているんだと思います。
私たちも商売としての側面を持ちながら、それだけではなくて、物の見方や伝え方、人への届け方に工夫や想いを込めています。そういった一つひとつの積み重ねが、これから先へと続いていく大事な力になると信じています。
取材を終えて 新田源太郎様の心意気とは
人から人へと紡いでいく想い
源太郎さんの心意気は、地域への感謝をかたちにしながら、未来の子どもたちに文化やもの作りの楽しさを伝えていく姿に表れています。
「やってみねどわがんねべ!」という言葉の通り、まずやってみる、その一歩を大切にしながら、紅花染めを通じて心と技をつないでいます。どんな時代になっても、想いや姿勢は人から人へ受け継がれていく、そんなあたたかな信念が、今の活動の根っこにあるように感じました。